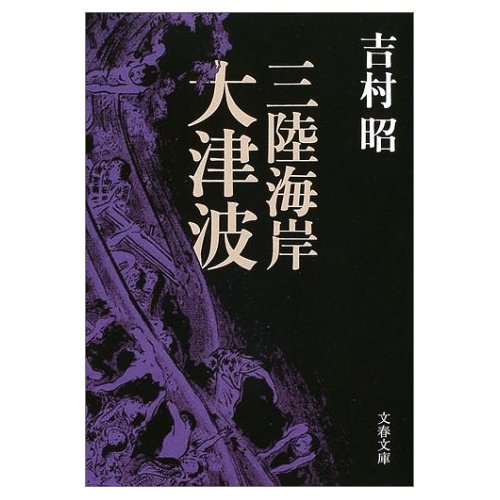『三陸海岸大津波』は、吉村昭が明治29年の大津波、昭和8年の大津波、昭和35年のチリ地震津波、三度の大津波の被災地である三陸海岸を歩きながら、古老から聞き取った記録文学である。今回の大災害によって、再び注目されている。
以下は、「ものろぎゃ・そりてえる」というブログに掲載されたものである。もう一度読み直し、なぜまた大津波の被害にあったのか、復興はどうあるべきかを考えなければならないと思う(伊藤)。
ものろぎゃ・そりてえる(2011年3月15日 (火))
吉村昭『三陸海岸大津波』
昨年、出張で石巻へ行く機会があった。仙石線の車輌にゆっくり揺られて松島を過ぎ、海がすぐそばまで迫る光景を眺めながら、穏やかできれいな海だなあ、と思っていたまさにその海がかくも甚大な災害を及ぼすことになろうとは、ただただ茫然とするばかりだ。
吉村昭『三陸海岸大津波』(文春文庫、2006年)は当初、『海の壁』というタイトルで1970年に中公新書から刊行されたが、版元を変えながら版が重ねられている。これまでも明治二十九年の大津波、昭和八年の大津波、昭和三十五年のチリ地震津波、三度の大津波で膨大な人命が奪われてきた三陸海岸一帯。吉村は青森、岩手、宮城にかけて複雑に織り成されたリアス式海岸の美しい眺望にひかれてたびたび訪れ、小説の舞台にも使うほど思い入れを抱いていた。三陸海岸を歩きながら、大津波を生き残った古老から話を聞き取り、当時を記録した文書の調査をして、とにかく足で稼いでまとめられた作品である。吉村らしい堅実な筆致に説得力がある記録文学だ。存命であれば第4章を加筆せねばならなかったところであろうか。
田老の堅牢な堤防を見てその殺伐とした姿に驚きながらも、これだけの備えをしなければいけない苦労をしのぶシーンがある。十メートルで万全とされていたが、今回の大津波ではこの大堤防も軽々と乗り越えられてしまった。場所によっては十メートルをはるかに越える高さまで波が押し寄せた可能性を記しており、波高把握の難しさの指摘が目を引く。
当時を生き残った人々の証言は時代こそ違えども、今回の被災者の体験とまさにリアルタイムで重なり、読み進めるのは少々つらい。係累を失って呆然とし、中には発狂してしまった人の姿も描かれている。今回の大災害にあたってもPTSDへのケアがこれから重要になってくるはずだ。明治、昭和の大津波はその当時にあって前例にない規模であり、普段の経験則が通用しなかったからこそ避難が遅れ、多くの人命を失ってしまった。そうした教訓は三陸海岸の各町では十分に意識されて対策に怠りはなかった。それでも想定を超える大地震・大津波に直面してしまったが、むしろ対策があったからこそ助かった人命もあったと考えるべきであろうか。想定を超えたのは自然災害の規模だけではない。原発事故という人間自身が生み出した災害にも翻弄されているところに、過去三度の大津波とは異なったテーマが見出されてくる。