2月1日、東京霞ヶ関の国土交通省の合同庁舎で開かれた
「航空・鉄道事故調査委員会」の「意見聴取会」を傍聴してきました。
このブログのタイトルだけを見て、ある種の期待を込めて
読まれる方には、ここに載せる感想は期待外れかもしれません。
当日は午前10時〜ということで、前日から新幹線で(最近よく乗る)上京しました。(なぜ東京なのか?)
事前に送られてきた傍聴券には、終了予定時刻の記載はなく、
当日行ってみて、なんと17時15分ごろが終了予定と分かりました。
普段から人の話を聞くのには慣れているし、また、それぞれに
興味深い意見公述でしたから、思ったよりはあっと言う間でした。

すべての意見公述に、メモを取って聞いていましたが、
冒頭の公述では、何故かあまりメモがありません。
(ある意味で予想を違わずということでしょうか・・・)
印象深かったのは、以下のお二人でした。
・黒田勲さん(日本ヒューマンファクター研究所所長)
・篠原一光さん(大阪大学大学院人間科学科助教授)
お二人が、公述の中で、期せずして同じ内容のことを
話されたのは意外でした。
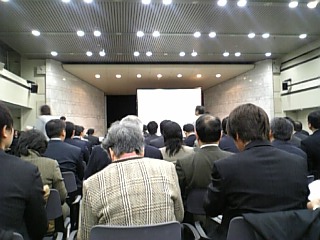
黒田さんの公述の最後の方で、「安全は生きている、
どんどん変化していく、だから学習していくべきものなのだ」
という話がありました。そういう観点からいくと、「JR西日本の
安全への取組み姿勢は10年ほど遅れている」と・・・。
また、「安全文化というものは、活き活きとひとりでに、自律的に
安全への方向性を作っていくことのできる文化だ」とも
言われました。
※写真は、お昼休みに行った屋上。
重い内容を話す10階とは裏腹な不思議な空間でした。

この点で、篠原さんも似たようなことを言われました。
やはり最後の方ですが、「注意集中を強制されるのではなく、
自発的に注意できるような環境や制度を整えるべきだ」と。
つまり、自発、自律的に、社員自らが「安全」に取り組める
「風土」が、ないということ。
風土というのは、風と土。今までのJR西日本の体質が、
動きようの無い「土」であるのなら、「風」を吹かせなければ
変わらないのではないか・・・?
「風」は、社内からだけで充分に起こるのだろうか?
大きく変えるために何が必要なのだろうか?
そんなことを考えながら聞いていました。

行って聞いてみないと分からないことが沢山あったという
意味では、体調も万全で無いなか、時間とお金をかけて
行った甲斐がありました。
また、冒頭の公述に対してのニュースの影響か、帰宅後、
この事故と直接的に関わりのない方々からも、「まだまだ
終わってないんだね」と声をかけられ、まだ二年も
経ってないのに、忘れられかけているこの事故のことが、
世間の人々の記憶の中で、もう一度呼び覚まされたという
意味では、この「意見聴取会」の意義は大きかったと思います。
また、何事も一人では出来ないのだということを、
皮肉な例で、改めて確信した「意見聴取会」でした。
様々な思いを抱えつつ帰路につく頃、あたりは、既に、
とっぷりと暮れていました。
※写真は、一番上と同じアングル(正面に国会議事堂を見る)
