・4月21日(木)午後1時半〜3時半
・会場:すばるホール(富田林市)
・講師:上倉 庸敬(かみくら つねゆき)先生(大阪大学名誉教授)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
**映画『東京物語』**
小津安二郎監督 1953年(昭和28) 松竹映画。出演=原節子、笠智衆、東山千栄子、杉村春子、山村聰、大阪志郎、香川京子他。
・原節子:本名 会田昌江。デビュ−15歳(1935年)、42歳で引退。その後、面会謝絶で一切のインタビュ−にも応じなかった。2015年9月逝去(95歳)。
○『東京物語』あらすじ
◆両親が上京
「尾道にいる両親(周吉・とめ)が上京。東京の片隅で小さな医院を開いている長男も、美容院を営んでいる長女も、毎日仕事が忙しくて両親をかまってやれない。そこに、優しく接したのが、戦死した次男の嫁の紀子だった。」
・老いた両親と子供たちの関係を通して、変貌していく戦後の家族のありようを描いている(子供たちは、東京の片隅で、自分たちの生活を支えるのが精一杯、老夫婦に冷たく邪険に扱う。)…その中で、仕事を休んで、歓待してくれたのは、紀子だった。

—
◇東京見物
「紀子(原節子)は、仕事を休んで、両親[平山周吉(笠智衆)、とめ(東山千栄子)]と、”はとバス”に乗って東京名所の観光に連れていく。…そして、帰りには、紀子の住んでいる質素なアパートに二人をまねいて、店屋物をとり、父の好きな酒でもてなしている。」
「長女・志げ(杉村春子)は、熱海の宿を数日予約して、両親に行ってもらうが、団体客が夜っぴいて遊んでおり熟睡できなかった。…志げの家に帰宅すると、早く帰ったことを露骨に嫌がられた。周吉は東京在住の友人たちを訪ね、とみは紀子のアパートを訪ねた。」
◆とみと紀子の会話 (*右上のシーン)…とみは紀子に再婚話をすすめる。〈とみ〉「でもなあ、だんだん歳をとってくるとやっぱり一人じゃ淋しいけーのう」 。〈紀子〉「いいんですの。あたし歳を取らないことにきめていますから」 。〈とみ〉「ええ人じゃのう」と、とみは涙ぐみ、感嘆する。
◇尾道に帰る
・子供たちからはあまり温かく接してもらえなかったが、それでも満足した表情をみせて尾道に帰った。東京からの帰路、大阪の三男・敬三(大阪志郎)のアパートにとまった二人の会話。〈周吉〉「子供たちは、なかなか親の思うようにはいかんもんじゃ。欲をいえば切りがない。ままええほうじゃよ」。 〈とみ〉「ええほうですとも。わたしたちは幸せでさあ。」

◇母が急な病で亡くなる
「両親が帰郷して数日もしないうちに、とみが危篤状態との電報が子供たちのもとに届いた。子供たちが尾道の実家に到着した翌日の未明にとみは死去した。…とみの葬儀が終わった後、長女・志げは次女の京子に形見の品をよこすように催促する。…紀子以外の子供たちは、葬儀が終わるとそそくさ帰って行った。…京子は憤慨するが紀子は義兄姉をかばい、若い京子をしずかに諭す。」
◇『東京物語』のクライマックス(*右上は、紀子が号泣する場面)
・紀子は、父親に東京へ帰る挨拶をする。いてくれて助かったと、むしろ父親のほうが例をいう。
〈父・周吉〉「お母さんも心配しとったけれど、…。ええところがあったら、いつでもお嫁に行っておくれ。もう、昌二(次男)のこたァ忘れてええんぢゃ。…(中略)」
〈紀子〉「いいえ、あたくし、そんな、おっしゃるほどのいい人間じゃありません。お父さんにまでそんな風に思って頂いたら、あたしの方こそ心苦しくて…(中略)」。
〈紀子〉「このごろ昌二さんのこと、思ひ出さない日さへあるんです。…」、「あたくし、いつまでもこのままぢゃいられないような気もするんです。…猾いんです」。
「いやァ、猾うはない」と、父親はつよく答えた。
・父親は、立ち上がって仏壇の引き出しから女物の時計をもってくる。「お母さんがちょうどあんたぐらいの時から持つとつたんぢゃ。形見に貰ってやっておくれ」。紀子は顔をおおう。
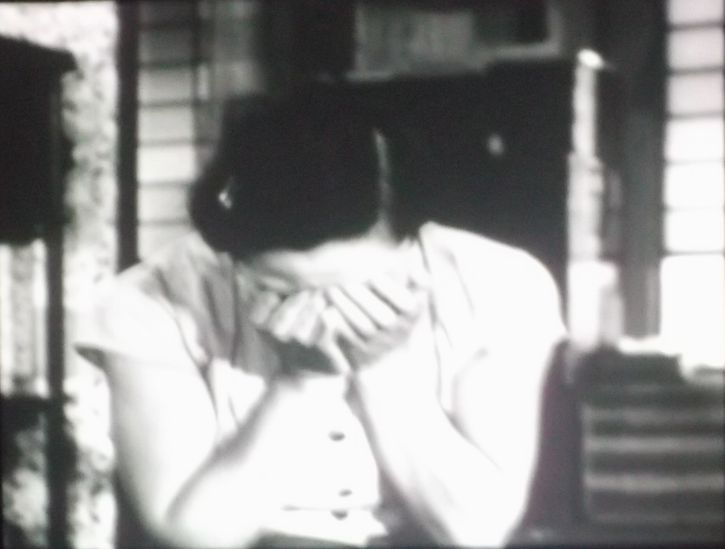
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
**あとがき**
・ラストに近く父の笠智衆が嫁の原節子に感謝の言葉を述べる場面はこの映画のクライマックス。良い相手がいたら再婚したほうがいいとすすめる笠に原節子が泣きくずれる場面は映画史に残るシーン。
・東京に去る列車の中で、形見の時計を両の手でしっかり握りしめる紀子(原節子)の場面で終わる。…無意味な生を生きている。生きていながら生きていないこの女性の、その張り詰めた思いは、父親の優しさに接して、ほとばしるように溶けていく。…母親の時を刻んだ時計をもらい、生きていくように、幸せになるように。
*参考資料
『絢爛たる影絵』−小津安二郎−(高橋治著、文芸春秋 1982年)
『生と死の文化史』(−日本映画における生と死ー)(上倉庸敬著他、懐徳堂記念会編)